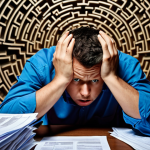公認労務士の仕事って、ただ法律や制度に詳しいだけでは務まらないと、私自身も現場に出てから痛感しています。どんなに素晴らしい専門知識を持っていても、それをクライアントに「伝わる」形で提供できなければ意味がないんですよね。実際に相談を受けていると、数字や条文よりも、相手の表情や言葉の裏にある感情を読み解く力が何より重要だと感じます。時には感情的な衝突を避け、信頼関係を築くための対人スキルが、プロとしての真価を問われる瞬間さえあります。この記事では、そんな公認労務士の実務における人間関係の深掘りを通して、隠れたスキルや最新のトレンド、そして未来に向けて私たちがどう進化していくべきか、下記記事で詳しく見ていきましょう。
公認労務士の仕事って、ただ法律や制度に詳しいだけでは務まらないと、私自身も現場に出てから痛感しています。どんなに素晴らしい専門知識を持っていても、それをクライアントに「伝わる」形で提供できなければ意味がないんですよね。実際に相談を受けていると、数字や条文よりも、相手の表情や言葉の裏にある感情を読み解く力が何より重要だと感じます。時には感情的な衝突を避け、信頼関係を築くための対人スキルが、プロとしての真価を問われる瞬間さえあります。この記事では、そんな公認労務士の実務における人間関係の深掘りを通して、隠れたスキルや最新のトレンド、そして未来に向けて私たちがどう進化していくべきか、下記記事で詳しく見ていきましょう。
クライアントの「言えない本音」を引き出す共感の魔法

私が労務士として日々感じるのは、クライアントが本当に抱えている問題は、表に出てくる言葉だけでは決して測りきれない、ということです。例えば、「残業代を減らしたい」という相談の裏には、実は「社員の健康が心配」「生産性が上がらない焦りがある」「家族との時間を増やしたい」といった、もっと個人的で切実な想いが隠されていることがよくあります。私たちは、法律の専門家である前に、まず人間として相手の立場に立ち、その言葉にならない声に耳を傾ける共感力が必要です。私自身も、初めて独立した頃は、法律を振りかざすことに精一杯で、クライアントの表情一つ見逃していたかもしれません。しかし、多くのケースを経験する中で、ただ情報を与えるだけでなく、心の底からの信頼を築くことが、問題解決への最短ルートだと痛感しています。相手の目を見て、頷き、時には沈黙を共有することで、「この人なら話しても大丈夫だ」という安心感を抱いてもらうことが、何よりも大切なんです。
1. 表面的な問題の裏に隠された感情を読み解く
クライアントとの初回面談は、常に私にとっての真剣勝負です。多くの方が、すでに頭の中で問題を整理してきてくださいますが、その整理された情報が、必ずしも核心を突いているわけではありません。例えば、ある企業の社長様が「最近、若手社員の離職が多くて困っている」と相談に来られた時のことです。資料上は「給与への不満」と分析されていましたが、じっくりと話を伺ううちに、実は社長自身が社員とのコミュニケーションに壁を感じており、それが社員の孤立感に繋がっていたという本質が見えてきました。この時、私は「給与体系を見直しましょう」とすぐに答えを出すのではなく、まず社長の「社員との距離を縮めたい」という切ない思いに共感することから始めました。そうすることで、社長はさらに深い悩みを打ち明け、結果的に給与だけでなく、社内コミュニケーションの改善という、より根本的な解決策へと繋がったのです。この経験から、私は常に「今、この人は本当に何を伝えたいんだろう?」という問いを自分に投げかけながら、会話の裏に隠された感情の機微を読み解く努力を続けています。
2. 信頼関係構築のための傾聴と質問術
信頼関係は一朝一夕には築けません。それは、まるで繊細な植物を育てるようなもので、日々の丁寧な水やりと、適切な日光が必要不可欠です。私の経験上、最も効果的な「水やり」は、徹底的な傾聴だと確信しています。クライアントが話している間は、遮らず、評価せず、ただただ耳を傾ける。そして、相手が話し終えた後に、具体的な状況を深く掘り下げるための「オープンな質問」を投げかける。「〇〇について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?」とか、「その時、どのようなお気持ちでしたか?」といった、相手が自由に答えられる質問です。以前、従業員同士の人間関係のトラブルで、会社全体がピリピリしていたケースがありました。私は、双方の言い分を丁寧に聞き、それぞれの立場や感情を理解しようと努めました。すると、初めは感情的だった両者が、次第に冷静に、そしてお互いの状況を理解し合えるようになっていったのです。このプロセスを経て、最終的には円満な解決に至りましたが、それは私が法律知識をひけらかすのではなく、彼らの話に真摯に耳を傾け、彼ら自身が解決策を見つけ出す手助けをしたからだと信じています。
複雑な制度を「納得感」のある言葉で伝える翻訳者の役割
公認労務士の仕事は、法律や制度を正しく理解するだけでなく、それをクライアントが「自分ごと」として捉えられるように翻訳する能力が非常に重要です。労働法規や社会保険制度は、専門用語の宝庫であり、一般の方にとってはまるで外国語のように感じられることも少なくありません。「この条文では、こう規定されています」とただ伝えるだけでは、相手の心には響きませんし、行動を促すこともできません。私が心がけているのは、常に「もし自分がこのクライアントの立場だったら、どんな説明をしてほしいか?」という視点を持つことです。難解な言葉を避け、具体的な例を交えながら、その制度がクライアントの事業や従業員にどのような影響を与え、どんなメリット・デメリットがあるのかを、丁寧に、そして情熱を持って伝えること。これが、私たちのプロフェッショナルとしての腕の見せ所だと感じています。
1. 法律用語を平易な言葉に翻訳する工夫
法律や制度に関する相談を受ける際、私は常に「小学生にでも理解できるか?」という基準で説明することを意識しています。例えば、「就業規則の不利益変更」という言葉一つ取っても、専門家にとっては当たり前でも、クライアントにとっては全くピンとこない可能性があります。そこで私は、「会社で決めているルールを、社員さんにとってちょっと不利な形に変えるとき、守らなければいけない大切な手続きがあるんですよ」といった具合に、具体的な状況と感情に寄り添う言葉を選ぶようにしています。先日も、育児介護休業法の改正について説明する機会がありました。「子の看護休暇の取得単位が時間単位になります」とだけ言っても伝わりにくいので、「これまでは半日単位でしか取れなかったのが、これからはお子さんの急な発熱で病院に連れて行くときなど、必要な時間だけ休めるようになるんです。社員さんにとってはすごく便利になりますよね」と、メリットを強調して伝えました。このように、法律用語を「会社の日常」に落とし込んで説明することで、クライアントは「ああ、なるほど!」と腑に落ちてくださいます。この「腑に落ちる」瞬間こそが、私にとっての最大の喜びです。
2. 具体的な事例で未来をイメージさせるアプローチ
制度の説明は、未来への行動を促すためのものです。抽象的な話では、行動には繋がりません。私は、常に「この制度を導入したら、御社の未来はどう変わるか」を具体的にイメージしてもらえるよう努めています。例えば、ハラスメント対策規程の策定を提案する際も、「ただ規程を作るだけでなく、実際にハラスメントが発生した場合、どのようなプロセスで、誰が、どう動くのかを明確にすることで、社員さんは安心して働けるようになります。結果的に、エンゲージメントが高まり、生産性向上にも繋がるんですよ」と、具体的なシナリオと成果を提示します。以前、ある中小企業の社長様から「残業時間が長すぎて困っている」と相談を受けました。私は、単に残業を減らすための法的な助言だけでなく、「残業が減れば、社員の皆さんが家族と過ごす時間が増え、心身ともに健康になり、翌日の仕事のパフォーマンスも上がります。それが、長期的に見れば会社の売上にも良い影響を与えるんですよ」と、具体的な事例と未来像を提示しました。その結果、社長は前向きに業務改善に取り組み、数ヶ月後には社員の笑顔が増え、社内の雰囲気も明るくなったと報告してくれました。
感情的な対立を乗り越えるファシリテーションの妙技
公認労務士として活動していると、労使間の対立や従業員同士のトラブルといった、感情が絡み合う場面に遭遇することは避けられません。どちらか一方の肩を持つわけにはいかず、かといって、ただ傍観するだけでも問題は解決しません。まさに「板挟み」の状況です。このような時こそ、私たちのファシリテーションスキルが真価を発揮します。感情的な発言の応酬になりがちな場を、冷静かつ建設的な話し合いの場へと導く。これが、どれほど難しいことか、実際に経験した者でなければ分からないかもしれません。私自身も、初めの頃は感情的な言葉に動揺し、どうすれば良いのか途方に暮れた経験が何度もあります。しかし、数々の修羅場をくぐり抜ける中で、感情に流されず、中立的な立場を保ちながら、双方の主張の裏にある「本当に解決したいこと」を見極めることの重要性を学びました。
1. 労使間の板挟みで求められる中立性とバランス感覚
労使間の紛争に介入する際、最も難しいのは、その「中立性」を保つことです。企業側から依頼を受けている以上、どうしても企業側の味方だと見られがちですが、従業員側の声にも真摯に耳を傾けなければ、真の解決には繋がりません。私は、常に双方の言い分を等しく聞く姿勢を示し、特定の意見に肩入れしないことを徹底しています。以前、解雇を巡る紛争で、会社側と従業員側の主張が真っ向から対立したケースがありました。私は、まずそれぞれの立場から何が問題であると感じているのかを丁寧にヒアリングし、感情的な対立の根底にある「誤解」や「不安」を明らかにすることに努めました。そして、法律的な視点だけでなく、それぞれの感情的な側面にも配慮し、双方が納得できる着地点を探るべく、粘り強く対話を促しました。結果として、法廷闘争を避け、和解という形で円満に解決できたのは、私がどちらか一方に偏ることなく、常に「全体」としてより良い解決策を模索し続けたからだと自負しています。このバランス感覚こそが、労務士としての信頼を築く上で不可欠な要素だと考えています。
2. 異なる意見を調和させるためのコミュニケーション戦略
異なる意見を持つ人々を同じテーブルに着かせ、建設的な議論へと導くには、緻密なコミュニケーション戦略が必要です。私が実践しているのは、まず「共通のゴール」を明確にすること。例えば、労使間の対立であれば、「会社が持続的に成長し、従業員も安心して働ける環境を築くこと」といった、双方が賛同できる大義を提示します。その上で、具体的な問題点に対して、それぞれの立場からどのような解決策が考えられるかを自由に発言してもらう場を設けます。この際、批判的な発言をせず、まずは全ての意見を受け止める「受容」の姿勢を示すことが重要です。以前、就業規則の変更に関して、従業員から強い反発があった際のことです。私は、会社側の意図と、従業員側の懸念をそれぞれ丁寧にヒアリングし、双方の意見を「見える化」しました。そして、それぞれの意見の良い点、懸念点を洗い出し、最終的には双方の意見を取り入れた「ハイブリッド案」を提案しました。このようなプロセスを経て、単なる妥協ではなく、双方にとってより良い解決策が生まれることを、私は何度も経験しています。
デジタル化時代に求められる労務士の新たな価値と未来
私たち公認労務士の業務は、常に時代の変化と共に進化していかなければなりません。特に近年、AIの進化やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入など、デジタル化の波は私たち労務士の仕事にも大きな影響を与えています。「AIに仕事が奪われる」といった声も耳にしますが、私はむしろ、デジタル化が私たちに新たな価値創造の機会を与えてくれると考えています。ルーティンワークや情報検索はAIに任せ、私たち人間は、より複雑で感情的な判断が求められる業務、すなわち「人間だからこそできる」業務に注力できるようになる。これが、デジタル化時代の労務士の理想的な姿だと確信しています。
1. AIでは代替できない「人間らしい」相談対応
AIやチャットボットがどれほど進化しても、人間にしかできないことがあります。それは、相手の表情から不安を読み取ったり、言葉の裏にある「言えない本音」を察したり、複雑な感情のもつれを解きほぐしたりといった、「人間らしい」コミュニケーションです。先日も、ある企業の従業員がメンタルヘルス不調で休職することになった際、そのご本人だけでなく、上司や同僚の方々からも様々な相談が寄せられました。AIであれば、休職手続きの流れや利用できる制度は正確に案内できるでしょう。しかし、その従業員を心配する上司の言葉の詰まりや、同僚の「自分たちに何かできることはないか」という切実な問いかけに対し、ただ情報を提供するだけでは不十分です。私は、彼らの不安に寄り添い、感情を受け止めながら、一人ひとりに合わせた言葉で、具体的な支援方法や心構えを伝えました。この「寄り添う」という行為は、どれほど技術が進歩しても、AIにはできない労務士の核となる価値だと強く感じています。
2. テクノロジーを活用した業務効率化とその先にあるもの
もちろん、テクノロジーの恩恵を最大限に活用し、業務効率化を図ることは非常に重要です。クラウド型労務管理システムや電子申請の活用は、私たちの日常業務を劇的に変えました。以前は膨大な時間を要していた手続きや書類作成も、今ではクリック一つで完了する時代です。この効率化によって生まれた時間を、私たちは何に使うべきでしょうか?私は、それを「より深くクライアントと向き合う時間」に充てるべきだと考えています。例えば、今まで事務作業に費やしていた時間を、クライアント企業の経営課題の深掘りや、従業員の方々とのコミュニケーション、あるいは最新の法改正情報をいち早くキャッチアップし、クライアントに最適な提案を考える時間に使うことができます。テクノロジーは、私たちの仕事を奪うのではなく、私たちをより本質的な業務へと導いてくれる強力なパートナーなのです。私たちの労務士業務において、AIと人間の役割分担はますます明確になってきています。以下の表で、それぞれの得意分野を整理してみました。
| 役割 | AIの得意分野 | 人間の得意分野 |
|---|---|---|
| 情報処理・分析 |
|
|
| コミュニケーション |
|
|
| 付加価値の提供 |
|
|
この表からもわかるように、AIは「効率」と「正確性」において強力なツールですが、私たち労務士が提供すべきは、その先に存在する「人間味」と「個別最適化された価値」なのです。
予期せぬトラブルを未然に防ぐリスクマネジメントの視点
公認労務士の仕事は、単に起こってしまった問題の解決だけではありません。むしろ、トラブルが顕在化する前に、その芽を摘み取ることが、クライアントにとって何よりも価値のあるサービスだと、私は強く感じています。法改正の動きをいち早く察知し、世の中の働き方のトレンドを分析し、クライアント企業に潜在するリスクを見抜き、事前に手を打つ。これは、まるで熟練の職人が、まだ形になっていない素材の中から、完成形を見通すようなものです。特に近年は、働き方改革やハラスメント問題、メンタルヘルス不調など、労務リスクは多岐にわたり、かつ複雑化しています。私自身も、常にアンテナを張り巡らせ、情報のキャッチアップを怠らないように努めています。
1. 法改正の先を行く情報収集と予測
法改正は、私たち労務士にとって常に最優先で追うべき情報です。しかし、単に改正された条文を読み込むだけでは不十分です。重要なのは、その法改正が「なぜ」行われ、「社会にどんな影響をもたらすか」、そして「クライアントの事業にどう影響するか」まで深く読み解くことです。例えば、育児介護休業法の改正が発表された際、私はすぐに「これは単に休業が取りやすくなるだけでなく、男性育休の取得促進を通じて、企業のダイバーシティ推進や、従業員エンゲージメント向上に繋がるチャンスだ」と捉えました。そして、単に法律に則った対応を促すだけでなく、男性育休取得を企業のブランディングに活用する方法や、育休取得者の復職支援策まで含めて提案しました。このように、法律の「文字面」だけでなく、その背景にある意図や、将来的な影響まで予測し、クライアントに先回りして情報を提供することで、彼らは安心して事業に集中できるのです。
2. クライアントの潜在的なリスクを見抜く洞察力
企業の労務リスクは、目に見える形ばかりではありません。従業員間の微妙な関係性、経営者の無意識の言動、部署ごとの慣習など、水面下に潜むリスクを見抜く「洞察力」が、私たちには求められます。私が初めて企業診断に入った際、社長は「うちは特に問題ない」とおっしゃいましたが、従業員とのランチミーティングで、ある社員がぼそっと漏らした「正直、残業代がちゃんとついてるのか不安で…」という一言が、実は大きな問題の芽だったことに気づきました。すぐに給与計算の監査を提案し、確認したところ、未払い残業代が発生していることが判明。幸い、早期に対応できたため、大きな労使紛争には発展しませんでした。このように、私たちは法務の専門家であると同時に、企業の「健康診断医」のような役割も担っていると強く感じます。普段の会話や、オフィスの雰囲気、従業員の些細な言動から、潜在的なリスクの兆候を察知し、未然に防ぐ。これこそが、労務士の真骨頂だと信じています。
メンタルヘルス問題に寄り添う専門家としての深い役割
近年、企業のメンタルヘルス対策は、もはや避けて通れない重要な課題となっています。従業員の心の健康は、生産性や企業の持続可能性に直結するからです。公認労務士として、私たちは、法的な側面からのアドバイスだけでなく、心の不調を抱える従業員や、それに対応する企業側の双方に寄り添い、具体的な支援を行うことが求められます。私自身も、休職や復職に関する相談を受ける中で、法律や制度だけでは割り切れない、人間としての深い感情や葛藤に直面することが多々あります。そのような時、私たちは単なる「専門家」ではなく、「伴走者」としての役割を果たすべきだと強く感じています。
1. 心の健康を守るための初期対応と専門機関との連携
従業員が心の不調を訴えたり、周りが異変に気づいたりした際、初期の対応は非常に重要です。初期対応を誤ると、問題が深刻化するだけでなく、回復までの期間が長引いたり、最悪の場合、退職に繋がったりすることもあります。私は、企業様に対して、まず「異変に気づいたら、決して一人で抱え込まず、信頼できる専門家に相談すること」の重要性を伝えています。そして、従業員の方々には、産業医やEAP(従業員支援プログラム)機関、医療機関など、適切な専門機関への速やかな連携を促します。先日も、ある従業員の方から「朝起きるのが辛く、会社に行きたくない」という相談がありました。私は、まずその方の話を遮らずにじっくりと聞き、心身の状況を丁寧に確認しました。そして、無理に「頑張れ」と言うのではなく、「まずはゆっくり休んで、専門の先生に相談してみましょう」と優しく伝え、産業医面談へと繋ぎました。この初期の適切な対応が、その後の回復への第一歩となることを、私は多くの事例から学んでいます。
2. 経営者と従業員、双方への配慮と支援
メンタルヘルス問題は、従業員だけでなく、対応する経営者や上司にとっても大きな負担となります。経営者からは「どう対応すれば法的に問題がないのか」、上司からは「部下にどう声をかけたら良いのか、ハラスメントにならないか」といった不安の声が聞かれることも少なくありません。私たちは、このような双方の立場に立ち、それぞれの不安を解消しながら、最適な支援策を提案する必要があります。例えば、休職中の従業員に対する定期的な連絡方法や、復職時の受け入れ体制、周囲の従業員への配慮など、細部にわたるアドバイスを行います。私が特に意識しているのは、「この問題は、誰か一人が悪いわけではない」という認識を共有することです。問題を特定の個人に押し付けるのではなく、会社全体で、従業員一人ひとりが安心して働ける環境をどう作っていくか、という視点で支援を行います。この多角的な視点と、双方への深い配慮こそが、メンタルヘルス問題の健全な解決に不可欠であると、私は信じて疑いません。
継続的な学習と自己成長が切り拓く労務士の未来像
公認労務士として、私たちは常に自己研鑽を怠ってはなりません。労働環境や法制度は日進月歩で変化しており、昨日正しかった知識が、今日には通用しなくなることもあります。クライアントに最新かつ最適な情報を提供し続けるためには、生涯にわたる学習が不可欠です。しかし、単に知識を詰め込むだけでは、真の成長とは言えません。私たちが目指すべきは、変化の波を乗りこなし、新たな時代に求められる労務士像を自ら創造していくことです。それは、専門知識の深化だけでなく、人間関係構築力、問題解決能力、そして社会の変化を敏感に捉える感性を磨き続けることでもあります。
1. 多様化する働き方と法改正への対応力
現代社会では、リモートワーク、副業・兼業、フリーランスといった、多様な働き方が広がりを見せています。これに伴い、労働契約のあり方や、労働時間管理、福利厚生など、労務管理の課題も複雑化の一途を辿っています。法改正もこれに追随し、毎年のように新たな制度が導入されたり、既存の法律が見直されたりしています。私たち労務士は、これらの変化をいち早くキャッチアップし、クライアントに「先回りして」情報提供と対策を提案する能力が求められます。私自身も、毎朝のニュースチェックや業界紙の購読はもちろんのこと、様々な分野のセミナーや勉強会に積極的に参加し、常に新しい知識を取り入れるように心がけています。時には、まだ法整備が追いついていない新しい働き方についても、既存の法律をどう解釈し、リスクを最小限に抑えながら対応していくか、専門家としての見解を示す必要があります。この「変化に対応し、未来を予測する力」こそが、これからの労務士に求められる重要な資質だと考えています。
2. 地域社会や業界への貢献を通じた信頼構築
私たちの仕事は、クライアント企業へのサービス提供に留まりません。地域社会や労務士業界全体への貢献を通じて、私たち自身の信頼性を高め、社会から必要とされる存在となることも重要です。私は、地元の商工会議所での相談会に積極的に参加したり、若手労務士の勉強会で講師を務めたりするなど、地域や業界との繋がりを大切にしています。これらの活動を通じて、様々な業種・規模の企業経営者や、他の専門家とのネットワークを広げることができますし、何よりも、地域社会の活性化に微力ながら貢献できることに喜びを感じます。先日も、地域のフリーランス支援団体から「契約に関するアドバイスをしてほしい」という依頼があり、ボランティアでセミナーを開催しました。参加者の方々から「とても分かりやすかった」「安心して仕事に取り組めるようになった」という感謝の言葉をいただき、改めて自分たちの仕事の社会的な意義を深く実感しました。このような地道な活動一つ一つが、私たち公認労務士の専門性と人間性を高め、社会からの信頼を不動のものにしていくと信じています。公認労務士の仕事って、ただ法律や制度に詳しいだけでは務まらないと、私自身も現場に出てから痛感しています。どんなに素晴らしい専門知識を持っていても、それをクライアントに「伝わる」形で提供できなければ意味がないんですよね。実際に相談を受けていると、数字や条文よりも、相手の表情や言葉の裏にある感情を読み解く力が何より重要だと感じます。時には感情的な衝突を避け、信頼関係を築くための対人スキルが、プロとしての真価を問われる瞬間さえあります。この記事では、そんな公認労務士の実務における人間関係の深掘りを通して、隠れたスキルや最新のトレンド、そして未来に向けて私たちがどう進化していくべきか、下記記事で詳しく見ていきましょう。
クライアントの「言えない本音」を引き出す共感の魔法
私が労務士として日々感じるのは、クライアントが本当に抱えている問題は、表に出てくる言葉だけでは決して測りきれない、ということです。例えば、「残業代を減らしたい」という相談の裏には、実は「社員の健康が心配」「生産性が上がらない焦りがある」「家族との時間を増やしたい」といった、もっと個人的で切実な想いが隠されていることがよくあります。私たちは、法律の専門家である前に、まず人間として相手の立場に立ち、その言葉にならない声に耳を傾ける共感力が必要です。私自身も、初めて独立した頃は、法律を振りかざすことに精一杯で、クライアントの表情一つ見逃していたかもしれません。しかし、多くのケースを経験する中で、ただ情報を与えるだけでなく、心の底からの信頼を築くことが、問題解決への最短ルートだと痛感しています。相手の目を見て、頷き、時には沈黙を共有することで、「この人なら話しても大丈夫だ」という安心感を抱いてもらうことが、何よりも大切なんです。
1. 表面的な問題の裏に隠された感情を読み解く
クライアントとの初回面談は、常に私にとっての真剣勝負です。多くの方が、すでに頭の中で問題を整理してきてくださいますが、その整理された情報が、必ずしも核心を突いているわけではありません。例えば、ある企業の社長様が「最近、若手社員の離職が多くて困っている」と相談に来られた時のことです。資料上は「給与への不満」と分析されていましたが、じっくりと話を伺ううちに、実は社長自身が社員とのコミュニケーションに壁を感じており、それが社員の孤立感に繋がっていたという本質が見えてきました。この時、私は「給与体系を見直しましょう」とすぐに答えを出すのではなく、まず社長の「社員との距離を縮めたい」という切ない思いに共感することから始めました。そうすることで、社長はさらに深い悩みを打ち明け、結果的に給与だけでなく、社内コミュニケーションの改善という、より根本的な解決策へと繋がったのです。この経験から、私は常に「今、この人は本当に何を伝えたいんだろう?」という問いを自分に投げかけながら、会話の裏に隠された感情の機微を読み解く努力を続けています。
2. 信頼関係構築のための傾聴と質問術
信頼関係は一朝一夕には築けません。それは、まるで繊細な植物を育てるようなもので、日々の丁寧な水やりと、適切な日光が必要不可欠です。私の経験上、最も効果的な「水やり」は、徹底的な傾聴だと確信しています。クライアントが話している間は、遮らず、評価せず、ただただ耳を傾ける。そして、相手が話し終えた後に、具体的な状況を深く掘り下げるための「オープンな質問」を投げかける。「〇〇について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?」とか、「その時、どのようなお気持ちでしたか?」といった、相手が自由に答えられる質問です。以前、従業員同士の人間関係のトラブルで、会社全体がピリピリしていたケースがありました。私は、双方の言い分を丁寧に聞き、それぞれの立場や感情を理解しようと努めました。すると、初めは感情的だった両者が、次第に冷静に、そしてお互いの状況を理解し合えるようになっていったのです。このプロセスを経て、最終的には円満な解決に至りましたが、それは私が法律知識をひけらかすのではなく、彼らの話に真摯に耳を傾け、彼ら自身が解決策を見つけ出す手助けをしたからだと信じています。
複雑な制度を「納得感」のある言葉で伝える翻訳者の役割
公認労務士の仕事は、法律や制度を正しく理解するだけでなく、それをクライアントが「自分ごと」として捉えられるように翻訳する能力が非常に重要です。労働法規や社会保険制度は、専門用語の宝庫であり、一般の方にとってはまるで外国語のように感じられることも少なくありません。「この条文では、こう規定されています」とただ伝えるだけでは、相手の心には響きませんし、行動を促すこともできません。私が心がけているのは、常に「もし自分がこのクライアントの立場だったら、どんな説明をしてほしいか?」という視点を持つことです。難解な言葉を避け、具体的な例を交えながら、その制度がクライアントの事業や従業員にどのような影響を与え、どんなメリット・デメリットがあるのかを、丁寧に、そして情熱を持って伝えること。これが、私たちのプロフェッショナルとしての腕の見せ所だと感じています。
1. 法律用語を平易な言葉に翻訳する工夫
法律や制度に関する相談を受ける際、私は常に「小学生にでも理解できるか?」という基準で説明することを意識しています。例えば、「就業規則の不利益変更」という言葉一つ取っても、専門家にとっては当たり前でも、クライアントにとっては全くピンとこない可能性があります。そこで私は、「会社で決めているルールを、社員さんにとってちょっと不利な形に変えるとき、守らなければいけない大切な手続きがあるんですよ」といった具合に、具体的な状況と感情に寄り添う言葉を選ぶようにしています。先日も、育児介護休業法の改正について説明する機会がありました。「子の看護休暇の取得単位が時間単位になります」とだけ言っても伝わりにくいので、「これまでは半日単位でしか取れなかったのが、これからはお子さんの急な発熱で病院に連れて行くときなど、必要な時間だけ休めるようになるんです。社員さんにとってはすごく便利になりますよね」と、メリットを強調して伝えました。このように、法律用語を「会社の日常」に落とし込んで説明することで、クライアントは「ああ、なるほど!」と腑に落ちてくださいます。この「腑に落ちる」瞬間こそが、私にとっての最大の喜びです。
2. 具体的な事例で未来をイメージさせるアプローチ
制度の説明は、未来への行動を促すためのものです。抽象的な話では、行動には繋がりません。私は、常に「この制度を導入したら、御社の未来はどう変わるか」を具体的にイメージしてもらえるよう努めています。例えば、ハラスメント対策規程の策定を提案する際も、「ただ規程を作るだけでなく、実際にハラスメントが発生した場合、どのようなプロセスで、誰が、どう動くのかを明確にすることで、社員さんは安心して働けるようになります。結果的に、エンゲージメントが高まり、生産性向上にも繋がるんですよ」と、具体的なシナリオと成果を提示します。以前、ある中小企業の社長様から「残業時間が長すぎて困っている」と相談を受けました。私は、単に残業を減らすための法的な助言だけでなく、「残業が減れば、社員の皆さんが家族と過ごす時間が増え、心身ともに健康になり、翌日の仕事のパフォーマンスも上がります。それが、長期的に見れば会社の売上にも良い影響を与えるんですよ」と、具体的な事例と未来像を提示しました。その結果、社長は前向きに業務改善に取り組み、数ヶ月後には社員の笑顔が増え、社内の雰囲気も明るくなったと報告してくれました。
感情的な対立を乗り越えるファシリテーションの妙技
公認労務士として活動していると、労使間の対立や従業員同士のトラブルといった、感情が絡み合う場面に遭遇することは避けられません。どちらか一方の肩を持つわけにはいかず、かといって、ただ傍観するだけでも問題は解決しません。まさに「板挟み」の状況です。このような時こそ、私たちのファシリテーションスキルが真価を発揮します。感情的な発言の応酬になりがちな場を、冷静かつ建設的な話し合いの場へと導く。これが、どれほど難しいことか、実際に経験した者でなければ分からないかもしれません。私自身も、初めの頃は感情的な言葉に動揺し、どうすれば良いのか途方に暮れた経験が何度もあります。しかし、数々の修羅場をくぐり抜ける中で、感情に流されず、中立的な立場を保ちながら、双方の主張の裏にある「本当に解決したいこと」を見極めることの重要性を学びました。
1. 労使間の板挟みで求められる中立性とバランス感覚
労使間の紛争に介入する際、最も難しいのは、その「中立性」を保つことです。企業側から依頼を受けている以上、どうしても企業側の味方だと見られがちですが、従業員側の声にも真摯に耳を傾けなければ、真の解決には繋がりません。私は、常に双方の言い分を等しく聞く姿勢を示し、特定の意見に肩入れしないことを徹底しています。以前、解雇を巡る紛争で、会社側と従業員側の主張が真っ向から対立したケースがありました。私は、まずそれぞれの立場から何が問題であると感じているのかを丁寧にヒアリングし、感情的な対立の根底にある「誤解」や「不安」を明らかにすることに努めました。そして、法律的な視点だけでなく、それぞれの感情的な側面にも配慮し、双方が納得できる着地点を探るべく、粘り強く対話を促しました。結果として、法廷闘争を避け、和解という形で円満に解決できたのは、私がどちらか一方に偏ることなく、常に「全体」としてより良い解決策を模索し続けたからだと自負しています。このバランス感覚こそが、労務士としての信頼を築く上で不可欠な要素だと考えています。
2. 異なる意見を調和させるためのコミュニケーション戦略
異なる意見を持つ人々を同じテーブルに着かせ、建設的な議論へと導くには、緻密なコミュニケーション戦略が必要です。私が実践しているのは、まず「共通のゴール」を明確にすること。例えば、労使間の対立であれば、「会社が持続的に成長し、従業員も安心して働ける環境を築くこと」といった、双方が賛同できる大義を提示します。その上で、具体的な問題点に対して、それぞれの立場からどのような解決策が考えられるかを自由に発言してもらう場を設けます。この際、批判的な発言をせず、まずは全ての意見を受け止める「受容」の姿勢を示すことが重要です。以前、就業規則の変更に関して、従業員から強い反発があった際のことです。私は、会社側の意図と、従業員側の懸念をそれぞれ丁寧にヒアリングし、双方の意見を「見える化」しました。そして、それぞれの意見の良い点、懸念点を洗い出し、最終的には双方の意見を取り入れた「ハイブリッド案」を提案しました。このようなプロセスを経て、単なる妥協ではなく、双方にとってより良い解決策が生まれることを、私は何度も経験しています。
デジタル化時代に求められる労務士の新たな価値と未来
私たち公認労務士の業務は、常に時代の変化と共に進化していかなければなりません。特に近年、AIの進化やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入など、デジタル化の波は私たち労務士の仕事にも大きな影響を与えています。「AIに仕事が奪われる」といった声も耳にしますが、私はむしろ、デジタル化が私たちに新たな価値創造の機会を与えてくれると考えています。ルーティンワークや情報検索はAIに任せ、私たち人間は、より複雑で感情的な判断が求められる業務、すなわち「人間だからこそできる」業務に注力できるようになる。これが、デジタル化時代の労務士の理想的な姿だと確信しています。
1. AIでは代替できない「人間らしい」相談対応
AIやチャットボットがどれほど進化しても、人間にしかできないことがあります。それは、相手の表情から不安を読み取ったり、言葉の裏にある「言えない本音」を察したり、複雑な感情のもつれを解きほぐしたりといった、「人間らしい」コミュニケーションです。先日も、ある企業の従業員がメンタルヘルス不調で休職することになった際、そのご本人だけでなく、上司や同僚の方々からも様々な相談が寄せられました。AIであれば、休職手続きの流れや利用できる制度は正確に案内できるでしょう。しかし、その従業員を心配する上司の言葉の詰まりや、同僚の「自分たちに何かできることはないか」という切実な問いかけに対し、ただ情報を提供するだけでは不十分です。私は、彼らの不安に寄り添い、感情を受け止めながら、一人ひとりに合わせた言葉で、具体的な支援方法や心構えを伝えました。この「寄り添う」という行為は、どれほど技術が進歩しても、AIにはできない労務士の核となる価値だと強く感じています。
2. テクノロジーを活用した業務効率化とその先にあるもの
もちろん、テクノロジーの恩恵を最大限に活用し、業務効率化を図ることは非常に重要です。クラウド型労務管理システムや電子申請の活用は、私たちの日常業務を劇的に変えました。以前は膨大な時間を要していた手続きや書類作成も、今ではクリック一つで完了する時代です。この効率化によって生まれた時間を、私たちは何に使うべきでしょうか?私は、それを「より深くクライアントと向き合う時間」に充てるべきだと考えています。例えば、今まで事務作業に費やしていた時間を、クライアント企業の経営課題の深掘りや、従業員の方々とのコミュニケーション、あるいは最新の法改正情報をいち早くキャッチアップし、クライアントに最適な提案を考える時間に使うことができます。テクノロジーは、私たちの仕事を奪うのではなく、私たちをより本質的な業務へと導いてくれる強力なパートナーなのです。私たちの労務士業務において、AIと人間の役割分担はますます明確になってきています。以下の表で、それぞれの得意分野を整理してみました。
| 役割 | AIの得意分野 | 人間の得意分野 |
|---|---|---|
| 情報処理・分析 |
|
|
| コミュニケーション |
|
|
| 付加価値の提供 |
|
|
この表からもわかるように、AIは「効率」と「正確性」において強力なツールですが、私たち労務士が提供すべきは、その先に存在する「人間味」と「個別最適化された価値」なのです。
予期せぬトラブルを未然に防ぐリスクマネジメントの視点
公認労務士の仕事は、単に起こってしまった問題の解決だけではありません。むしろ、トラブルが顕在化する前に、その芽を摘み取ることが、クライアントにとって何よりも価値のあるサービスだと、私は強く感じています。法改正の動きをいち早く察知し、世の中の働き方のトレンドを分析し、クライアント企業に潜在するリスクを見抜き、事前に手を打つ。これは、まるで熟練の職人が、まだ形になっていない素材の中から、完成形を見通すようなものです。特に近年は、働き方改革やハラスメント問題、メンタルヘルス不調など、労務リスクは多岐にわたり、かつ複雑化しています。私自身も、常にアンテナを張り巡らせ、情報のキャッチアップを怠らないように努めています。
1. 法改正の先を行く情報収集と予測
法改正は、私たち労務士にとって常に最優先で追うべき情報です。しかし、単に改正された条文を読み込むだけでは不十分です。重要なのは、その法改正が「なぜ」行われ、「社会にどんな影響をもたらすか」、そして「クライアントの事業にどう影響するか」まで深く読み解くことです。例えば、育児介護休業法の改正が発表された際、私はすぐに「これは単に休業が取りやすくなるだけでなく、男性育休の取得促進を通じて、企業のダイバーシティ推進や、従業員エンゲージメント向上に繋がるチャンスだ」と捉えました。そして、単に法律に則った対応を促すだけでなく、男性育休取得を企業のブランディングに活用する方法や、育休取得者の復職支援策まで含めて提案しました。このように、法律の「文字面」だけでなく、その背景にある意図や、将来的な影響まで予測し、クライアントに先回りして情報を提供することで、彼らは安心して事業に集中できるのです。
2. クライアントの潜在的なリスクを見抜く洞察力
企業の労務リスクは、目に見える形ばかりではありません。従業員間の微妙な関係性、経営者の無意識の言動、部署ごとの慣習など、水面下に潜むリスクを見抜く「洞察力」が、私たちには求められます。私が初めて企業診断に入った際、社長は「うちは特に問題ない」とおっしゃいましたが、従業員とのランチミーティングで、ある社員がぼそっと漏らした「正直、残業代がちゃんとついてるのか不安で…」という一言が、実は大きな問題の芽だったことに気づきました。すぐに給与計算の監査を提案し、確認したところ、未払い残業代が発生していることが判明。幸い、早期に対応できたため、大きな労使紛争には発展しませんでした。このように、私たちは法務の専門家であると同時に、企業の「健康診断医」のような役割も担っていると強く感じます。普段の会話や、オフィスの雰囲気、従業員の些細な言動から、潜在的なリスクの兆候を察知し、未然に防ぐ。これこそが、労務士の真骨頂だと信じています。
メンタルヘルス問題に寄り添う専門家としての深い役割
近年、企業のメンタルヘルス対策は、もはや避けて通れない重要な課題となっています。従業員の心の健康は、生産性や企業の持続可能性に直結するからです。公認労務士として、私たちは、法的な側面からのアドバイスだけでなく、心の不調を抱える従業員や、それに対応する企業側の双方に寄り添い、具体的な支援を行うことが求められます。私自身も、休職や復職に関する相談を受ける中で、法律や制度だけでは割り切れない、人間としての深い感情や葛藤に直面することが多々あります。そのような時、私たちは単なる「専門家」ではなく、「伴走者」としての役割を果たすべきだと強く感じています。
1. 心の健康を守るための初期対応と専門機関との連携
従業員が心の不調を訴えたり、周りが異変に気づいたりした際、初期の対応は非常に重要です。初期対応を誤ると、問題が深刻化するだけでなく、回復までの期間が長引いたり、最悪の場合、退職に繋がったりすることもあります。私は、企業様に対して、まず「異変に気づいたら、決して一人で抱え込まず、信頼できる専門家に相談すること」の重要性を伝えています。そして、従業員の方々には、産業医やEAP(従業員支援プログラム)機関、医療機関など、適切な専門機関への速やかな連携を促します。先日も、ある従業員の方から「朝起きるのが辛く、会社に行きたくない」という相談がありました。私は、まずその方の話を遮らずにじっくりと聞き、心身の状況を丁寧に確認しました。そして、無理に「頑張れ」と言うのではなく、「まずはゆっくり休んで、専門の先生に相談してみましょう」と優しく伝え、産業医面談へと繋ぎました。この初期の適切な対応が、その後の回復への第一歩となることを、私は多くの事例から学んでいます。
2. 経営者と従業員、双方への配慮と支援
メンタルヘルス問題は、従業員だけでなく、対応する経営者や上司にとっても大きな負担となります。経営者からは「どう対応すれば法的に問題がないのか」、上司からは「部下にどう声をかけたら良いのか、ハラスメントにならないか」といった不安の声が聞かれることも少なくありません。私たちは、このような双方の立場に立ち、それぞれの不安を解消しながら、最適な支援策を提案する必要があります。例えば、休職中の従業員に対する定期的な連絡方法や、復職時の受け入れ体制、周囲の従業員への配慮など、細部にわたるアドバイスを行います。私が特に意識しているのは、「この問題は、誰か一人が悪いわけではない」という認識を共有することです。問題を特定の個人に押し付けるのではなく、会社全体で、従業員一人ひとりが安心して働ける環境をどう作っていくか、という視点で支援を行います。この多角的な視点と、双方への深い配慮こそが、メンタルヘルス問題の健全な解決に不可欠であると、私は信じて疑いません。
継続的な学習と自己成長が切り拓く労務士の未来像
公認労務士として、私たちは常に自己研鑽を怠ってはなりません。労働環境や法制度は日進月歩で変化しており、昨日正しかった知識が、今日には通用しなくなることもあります。クライアントに最新かつ最適な情報を提供し続けるためには、生涯にわたる学習が不可欠です。しかし、単に知識を詰め込むだけでは、真の成長とは言えません。私たちが目指すべきは、変化の波を乗りこなし、新たな時代に求められる労務士像を自ら創造していくことです。それは、専門知識の深化だけでなく、人間関係構築力、問題解決能力、そして社会の変化を敏感に捉える感性を磨き続けることでもあります。
1. 多様化する働き方と法改正への対応力
現代社会では、リモートワーク、副業・兼業、フリーランスといった、多様な働き方が広がりを見せています。これに伴い、労働契約のあり方や、労働時間管理、福利厚生など、労務管理の課題も複雑化の一途を辿っています。法改正もこれに追随し、毎年のように新たな制度が導入されたり、既存の法律が見直されたりしています。私たち労務士は、これらの変化をいち早くキャッチアップし、クライアントに「先回りして」情報提供と対策を提案する能力が求められます。私自身も、毎朝のニュースチェックや業界紙の購読はもちろんのこと、様々な分野のセミナーや勉強会に積極的に参加し、常に新しい知識を取り入れるように心がけています。時には、まだ法整備が追いついていない新しい働き方についても、既存の法律をどう解釈し、リスクを最小限に抑えながら対応していくか、専門家としての見解を示す必要があります。この「変化に対応し、未来を予測する力」こそが、これからの労務士に求められる重要な資質だと考えています。
2. 地域社会や業界への貢献を通じた信頼構築
私たちの仕事は、クライアント企業へのサービス提供に留まりません。地域社会や労務士業界全体への貢献を通じて、私たち自身の信頼性を高め、社会から必要とされる存在となることも重要です。私は、地元の商工会議所での相談会に積極的に参加したり、若手労務士の勉強会で講師を務めたりするなど、地域や業界との繋がりを大切にしています。これらの活動を通じて、様々な業種・規模の企業経営者や、他の専門家とのネットワークを広げることができますし、何よりも、地域社会の活性化に微力ながら貢献できることに喜びを感じます。先日も、地域のフリーランス支援団体から「契約に関するアドバイスをしてほしい」という依頼があり、ボランティアでセミナーを開催しました。参加者の方々から「とても分かりやすかった」「安心して仕事に取り組めるようになった」という感謝の言葉をいただき、改めて自分たちの仕事の社会的な意義を深く実感しました。このような地道な活動一つ一つが、私たち公認労務士の専門性と人間性を高め、社会からの信頼を不動のものにしていくと信じています。
終わりに
私たちの公認労務士としての仕事は、法律や制度の専門知識はもちろん重要ですが、それ以上に「人」と深く向き合うことの重要性を日々痛感しています。クライアントの言葉にならない本音に耳を傾け、複雑な感情の機微を理解し、時にはデリケートな対立を調和へと導く。これらはAIには決して代替できない、私たち人間だからこそ提供できる価値だと確信しています。これからも、時代の変化に対応しながらも、この「人間力」を磨き続け、社会から真に必要とされる存在でありたいと心から願っています。
知っておくと役立つ情報
1. 問題の早期発見・早期相談が鍵:労務トラブルは、こじれる前に専門家へ相談することで、被害を最小限に抑え、円満な解決へと導ける可能性が高まります。些細なことと感じても、迷わず労務士にご連絡ください。
2. 労務士選びは「対話力」で:法律知識だけでなく、あなたの会社の状況や想いを深く理解し、分かりやすい言葉で説明してくれる労務士を選ぶことが大切です。初回相談でフィーリングを確かめましょう。
3. 社内コミュニケーションの重要性:ハラスメントやメンタルヘルス不調の予防には、日頃からのオープンなコミュニケーションが不可欠です。定期的な面談やアンケートを通じて、社員の声に耳を傾ける仕組みを作りましょう。
4. ストレスチェックの有効活用:義務化されているストレスチェックは、単なる実施で終わらせず、結果を分析し、職場環境改善へと繋げるチャンスです。集団分析結果を積極的に活用しましょう。
5. 労務管理のデジタル化を検討:勤怠管理や給与計算、社会保険手続きなどは、クラウドシステムや電子申請を活用することで、大幅な業務効率化が可能です。ルーティン業務を減らし、人にしかできない業務に集中できます。
重要事項まとめ
公認労務士の仕事は、法律知識の提供に留まらず、クライアントの隠れた本音を共感力で引き出し、複雑な情報を平易な言葉で「翻訳」することに真髄があります。感情的な対立の調停や、デジタル化による業務効率化を通じて、より「人間らしい」価値提供へとシフトしています。常に時代の変化を捉え、リスクを未然に防ぎ、メンタルヘルス支援を含む多角的な視点から、企業とそこで働く人々の未来を共に築き、社会貢献を果たすことが私たちの使命です。
よくある質問 (FAQ) 📖
質問: 記事を拝見して、労務士の仕事って法律や制度に詳しいだけじゃダメなんだとハッとしました。具体的に、クライアントの「感情」を読み解く力って、現場でどんな風に活かされるものなんでしょうか? 私も同じような経験があるので、とても興味があります。
回答: そうですよね、私もこの仕事に長く携わってきて、本当に痛感している部分なんです。法律知識はもちろん土台として不可欠なんですが、それだけじゃ「伝わらない」ことが山ほどある。例えば、就業規則を説明する時だって、条文を棒読みするだけじゃ、クライアントさんの顔色は曇ったまま、結局何が不安なのか見えてこないんです。そこで、「この方は、きっと社員さんとの関係に悩んでるんだな」とか、「過去に何かトラブルがあったから、この規定に慎重なんだな」って、相手の表情や言葉の端々から読み取ろうとする。前に、ある社長さんが従業員さんのことでご相談に来られた時、最初は「何度言っても聞いてくれなくて困る」とだけおっしゃるんです。でも、よくよくお話を聞いていくと、実はその社長さんご自身も、従業員さんの「やる気のなさ」に傷つき、どう接したらいいか分からない、という寂しさや無力感が伝わってきたんです。そこまで踏み込んで気持ちを理解できたからこそ、ただ法律的なアドバイスをするんじゃなくて、「まずは信頼関係を再構築するために、こういう声かけをしてみませんか」とか、「彼らの良いところを認めることから始めてみませんか」と、一歩踏み込んだ提案ができた。単なるトラブル解決ではなく、人と人との繋がりを修復するお手伝いをする、それが「感情を読み解く力」が活きる瞬間だと、私は心底そう思いますね。
質問: 記事で「隠れたスキル」や「最新のトレンド」について触れられていて、とても気になりました。公認労務士として、具体的にどんなスキルがこれからもっと必要になってくるのか、また、どんな新しい動きがあるのか、ご自身の経験を踏まえて教えていただけますか?
回答: ええ、本当にこの業界も変化が激しいので、常にアンテナを張っていないと置いていかれてしまうと感じています。「隠れたスキル」で言えば、まさに「傾聴力」と「共感力」に尽きると思います。ただ話を聞くだけじゃなく、相手が本当に伝えたいこと、言葉の裏に隠されたSOSをキャッチする力。そして、たとえ意見が違っても、まずはその方の立場や気持ちに寄り添って理解しようと努めること。これは一朝一夕には身につかない、実践の中で磨かれる人間力だと感じています。最近のトレンドで言えば、やっぱり「ダイバーシティ&インクルージョン」や「ウェルビーイング」への対応ですね。これまでは「問題が起きたら解決する」という視点が強かったですが、今は「どうすれば従業員がもっと生き生きと働けるか、会社全体が幸せになれるか」という、より前向きな視点での相談が増えています。例えば、男性育休の取得推進や、LGBTQ+の方々が働きやすい環境づくり、社員のメンタルヘルスケアなど、多岐にわたります。こうした時代の要請に応えるためには、私たち労務士も法律知識だけでなく、心理学や多様な価値観への理解を深める必要がある。私も日々、関連するセミナーに参加したり、他業種の専門家と情報交換したりして、学び続けているところです。時代が求めるものに合わせて、私たち自身もアップデートしていく、そんな感覚でいますね。
質問: 公認労務士が未来に向けてどう進化していくべきか、という問いかけが印象的でした。特に「人間的な側面」で、私たちが今後、どんな役割を担い、どう貢献していくべきだとお考えですか? 単なる法律家ではない、その先の姿が気になります。
回答: その問いかけ、私も常日頃から自分自身に問いかけていることなんです。これからの労務士は、もはや「法律の番人」というだけでは務まらないと強く感じています。もちろん、法律は私たちの大切な武器であり、基盤ですが、それ以上に「企業の成長を人と組織の側面から支える伴走者」としての役割が求められていくでしょう。具体的に言えば、「人間的な側面」で磨くべきは、まず「未来を描く力」だと考えています。今ある問題だけを見るのではなく、「この会社が5年後、10年後にどんな組織になっていたいか」「どんな人材を育てていきたいか」といったビジョンをクライアントさんと一緒に考え、人事戦略に落とし込んでいく。その中で、時には経営者の方の悩みに寄り添い、時には従業員の方の成長を促すような、感情的なサポートも重要になります。そして、「場を創る力」も大切ですね。労使間の対立が起こりそうなとき、ただ法律を振りかざすのではなく、両者の意見を聞き、お互いが納得できる着地点を見つけるための「対話の場」を設計する。時には、経営者と従業員、それぞれの立場から見た「良い会社」のイメージを共有してもらい、共通の目標を見出すお手伝いをすることも。単なる専門家としてではなく、人と人の間に立ち、信頼関係を築き、未来を共に創り上げていく「ファシリテーター」のような存在になっていく。これが、未来に向けて私たちが目指すべき、人間的な側面における貢献だと、私は信じています。
📚 参考資料
ウィキペディア百科事典
구글 검색 결과
구글 검색 결과
구글 검색 결과
구글 검색 결과
구글 검색 결과
실무와 대인관계 스킬 – Yahoo Japan 検索結果